【インテリア】新生活に合わせて机と椅子について考えてみた【家具】
投稿日:2021年04月28日
家がどうしようもないほど荒れている状態だったので断捨離とともに生活をちょこっと整えようと企ててるスタッフです。生活空間の課題の一つに「机と椅子」があります。
職場で座り、家でも座るという生活で1日の半分は寝て、半分は座っている不健康スタッフ。そのうち座りすぎてエコノミー症候群になるんじゃないかと思います。座りっぱなしでなんとなく疲れるし、腰もおしりも痛いです。

これでは老後の健康生活に悪い影響がでますね。
そこで改善策として
①椅子と机のサイズバランスを体に負担ないように調整する
②椅子と机との生活の仕方を変える
③運動する
を掲げました。
①椅子と机のサイズバランスの調整
職場の椅子が調整できるタイプなので机の高さと自分の身長から適した高さにします。それからPCの画面の高さも調整していこうと思います。
・まずポイントとして人間の自然な視線の方向。
椅子に座った状態だと目線は水平より約15度下がります。
・次に椅子の座面高。
椅子の座面高は身長の約1/4が目安とされています。作業用の場合はさらにマイナス1㎝程度低くするのがよいとされています。また机との差尺は座高の1/3を目安とされています。ちなみに座高は身長の0.55倍。
【例】
例えば身長160㎝だったら座高は160×0.55=88㎝
机と椅子座面の差は88㎝×1/3=約29㎝
机の高さが固定されているので他で調整していくとなると
机の高さ70㎝⇒椅子の座面がマイナス29㎝なので=41㎝
座面の高さ41㎝の椅子がよいということになりますね^^
※ヒールのある靴を履くときとぺたんこ靴の時で差があるのでその時の服装にも応じて調整が必要です。

今思うと学校の机と椅子は子供の成長に合わせて組み合わせ変えたりしてましたね。
で、椅子に座った時のPCモニターの高さの目安ですが、立った状態の目線の高さは身長の約0.9倍。身長と眼高の差が160㎝-(160×0.9)㎝=16㎝
座高の長さ+椅子の高さ-16㎝にすると座った時の眼高が出るので
(160㎝×0.55)+41㎝-16㎝=113㎝が目の高さそこから15度程度下がるとよいということは座った時の眼高にPC モニターの上端があるとモニターのいいところが自然な目線の先にある。ということになりそうです!
今だいぶモニター高めに設置してるし顔も上げ気味なのであんまりよろしくない姿勢だったかもしれません。まずはここから変えていきます。
θ=15度でa=目からPCまでの距離(底辺)が50㎝、b=直角に下がった辺とc=15度下がった先に延びる辺で直角三角形を作ったとしてWEBに計算してもらうと
b=約13.4㎝、c=約51.8㎝
モニターの中心が座った時の眼高113㎝-13.4㎝=99㎝くらいがいいらしいです。これってほぼほぼ机に直置きするくらいの高さの気もするんですけど、、、とにかく人間工学的な観点での楽な位置は
「画面は目線より低く!!」
これは自宅のテレビモニターにも応用できると思うのでぜひ皆さんも計算してみてください。
②椅子と机との生活の仕方を変える
自宅用の机と椅子も同じようにバランスを調整するのはいいとして、座りすぎの暮らしってどうなんでしょう。ということで強制的に立たせることにしました。
1)食事などは落ち着いて座る。
とはいえ食事は落ち着いて食べたいのでダイニングスペースは作ります。お気に入りの椅子とテーブルでくつろぎタイムができるようにします。
2)PCをいじる時や勉強をするときはなるべく立つ!?
仕事・勉強用の机を椅子に合わせたサイズにしないで起立した自分の身長に合わせます。カウンターテーブル的なものにして強制的に立って使うようにします。これで座りっぱなしを阻止。立つことで頭も案外スッキリするらしいので一石二鳥です。いよいよ疲れたらダイニングの椅子に座りに行っていったん休憩。という導線を作ります。
家具の使い方を制限することで生活導線を整える方式ですね。
くつろぎスペースとワークスペースを分けて飴と鞭でメリハリもばっちりです。

↑こんなイメージ
③は机と椅子と関係ないので省略します。適度に適当に運動します。
まとめ
椅子は生活するうえでとても重要だと思いますが、その時の自分自身の生活環境によって、あえて使わないというのも選択肢の一つです。使わなきゃという固定概念はひとまず脇に置いておきましょう!
ずっと同じ生活をコツコツ続ける中で、日々、私たちは変化していきます。それは家族の成長だったり、自分自身の体調であったり様々です。変化に合わせて
・家具のレイアウトを変える
・バリアフリーにする
・断熱を十分にする
・家を大きくしたり小さくしたりする
・家具を変える
加えたり、減らしたり。変化に合わせて無理なく住まいの環境を整えてみてはいかがでしょうか。暮らしで気になることがあれば何でもご相談ください。
群馬の沼田、前橋、高崎で自然素材の和モダン住宅を建てるなら鞍城建設へお問い合わせください。断熱性能や調湿性能にこだわり、省エネで人と環境にやさしい住まいをご提案します。注文住宅、平屋、リノベーション、二世帯住宅、数寄屋建築や土蔵リノベーションをお考えの方、暮らしを見直したい、住まいで気になることがる方、まずは無料相談会へご参加ください。
【お問い合わせ】
フリーダイヤル 0120-70-2711
または下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
【ZEHビルダー】目標と実績を更新しました【2021年度】
投稿日:2021年04月26日
【施工例】ランマのある家特集【和モダン】
投稿日:2021年04月23日
欄間が特徴的なスペースに注目して施工例を集めてみました。
皆さん欄間(ランマ)ってご存じでしょうか。天井と鴨居の間に設けられている開口部のことでです。装飾的な目的もあれば明り採りや通気の役割をしてくれることもあります。
欄間は大体がそのまま空洞になっているわけではなく、彫刻や格子、板、障子などが張られています。鴨居下の建具がシンプルな場合この欄間のデザインで空間の印象がガラッと変わるのでとても面白いのです。
ファッションも家も抜け感が大事ですね。
粋な欄間を取り入れてみませんか??
【和モダン】粋な部屋は欄間で差をつける!【通気・採光】
【施工例】住宅に組み込む仏間と仏壇【和モダン】
投稿日:2021年04月19日
施工例を更新しました。
今回は銘木をサラッと取り入れて住宅に組み込む仏間と仏壇をご紹介します。
設置を前提にすまいの一部として考えて作られているので、仰々しくなく、スッキリと見せることができます。
下記をクリック↓↓
【仏間シリーズ】住空間の仏間・仏壇【銘木建具】
【クリーニング】話題のスプリングクリーニングって何!?【年度初め】
投稿日:2021年04月15日
まず「スプリングクリーニング」とは
最近話題のスプリングクリーニングをご存じですか?
クリーニング=掃除ですが、日本では年末に大掃除するところを、欧米諸国では春の暖かくなったころに行うのが一般的なのだそうです。

日本だと年度初めで忙しくて掃除どころじゃないのでは!?しかも12月に大掃除したばかり。日本でこのスプリングクリーニングを取り入れる意味ってどんなことがあるのでしょうか。
春の大掃除メリットとデメリット
まずメリットとして次のことがあげられます。
【メリット】
・屋外作業のしやすやが段違い
・水仕事も苦にならない
窓を全開にしても寒くない!これ寒冷地は特に大事です。むしろ年末の大掃除をやめて春にやるのを正式な大掃除にしたいくらいです。玄関まわりもサクサクっと終わらせていましたが、春なら水を撒いたりしながら隅々まで丁寧に、掃除へ時間をかけやすいですね。

・洗濯ものが乾きやすい
・衣替えの季節なので収納の掃除ができる。
春の暖かく乾いた空気は洗濯にぴったり。冬ものの衣服やカーテン、ラグなども早く乾きます。冬と違って手がかじかむこともないのがいいですね!衣替えもささっとできそうです。
・年度切り替えのタイミングで断捨離
スタッフも新年度で断捨離真っ最中です。暖かいせいなのか、新年度だからなのか、不思議と冬よりもものを捨てるのに戸惑いがなく、素早い判断でものの仕分けができています。新調しなくてはいけないものがある時に、古いものをつい、保存してしまいがちですが、「新年度」という大義名分?で使わないものは躊躇なく地元のリサイクルセンターにもっていくなり、メルカリに出品するなり、あまりに保存状態が悪いものは思い切って捨てましょう。
捨てるときには分別も要注意です!
・湿度も温度も掃除に最適!?
・梅雨前の大掃除でカビ対策、
梅雨前に家じゅうに空気を通しておくことで湿気を除去、また浴室や洗面などカビの温床となりやすいところを早めにしっかりとお掃除しておくとカビ対策になりそうです。また暖房器具の埃を掃除すること…特にエアコンは暖房時期が終わったらそのまま夏にも使うので、一回掃除をしておくと夏の間気持ちよく使えます。
【デメリット】
いいところがたくさん出てきたところで、じゃあデメリットって何だい?っていう話ですよね。
・時期的にとにかく忙しい…これは人によると思いますが「子供さんの新学期の準備」「部署の移動」「決算の時期」「確定申告」など期限付きの仕事が山積みの季節でもあるので大掃除の余裕がない場合もあり。

・・・・くらいでしょうか。そもそも掃除にデメリットがあるのかもよくわかりません。笑
結局南極どうなん?
デメリットはやるうちに見えてくるかもしれませんが、今のところスプリングクリーニングいいことだらけですね。実際今、スタッフも家の大掃除をしておりますが、掃除しやすいことしやすいこと。まず水がそこまで冷たくない!!
昼間なら太陽光を浴びてちょうどいいくらいです。
断捨離もはかどりサクサクっと捨てられます。特に布類(衣服とかボロになってきたタオルとか、ありすぎるブランケットだとか必要以上にある防寒着だとか)には未練もなく仕分けして捨てる、雑巾にする、リサイクルにする。ということができています。これもきっと暖かいおかげ!!暑すぎないところがまた動くのにちょうどいいんですよね。
沼田市をはじめ寒冷地暮らしの方には特にお勧めのスプリングクリーニング。ぜひこの春から実践してみてはいかがでしょうか。
群馬の沼田、前橋、高崎で自然素材の和モダン住宅を建てるなら鞍城建設へ。
断熱性能や調湿性能にこだわり、省エネで人と環境にやさしい住まいをご提案します。注文住宅、平屋、リノベーション、二世帯住宅、数寄屋建築や土蔵リノベーションをご検討の方は無料相談会へお越しください。
【お問い合わせ】
フリーダイヤル 0120-70-2711
または下記のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
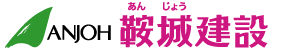
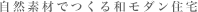
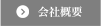
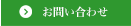
 0120-70-2711
0120-70-2711


